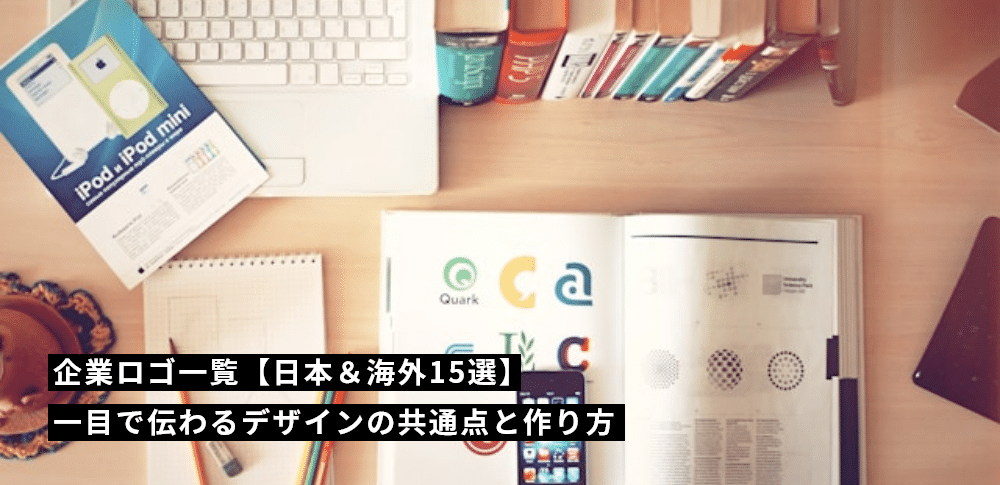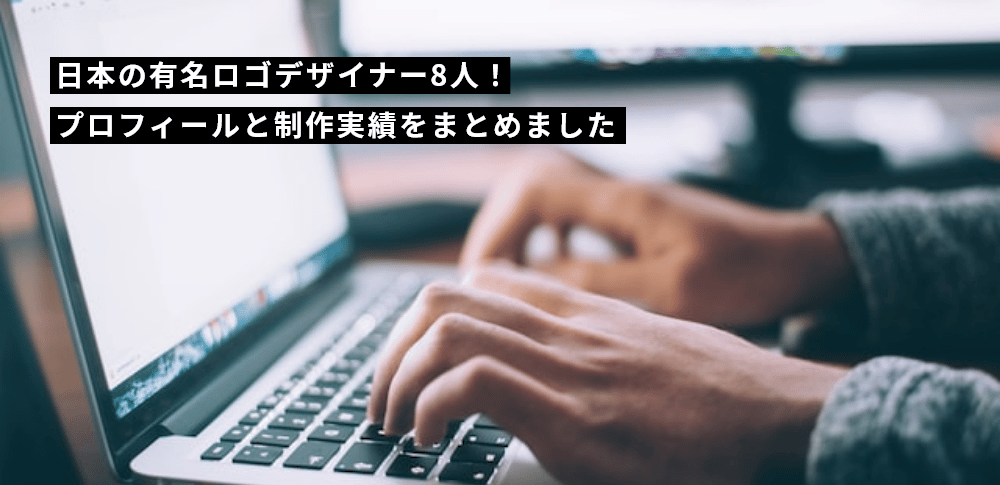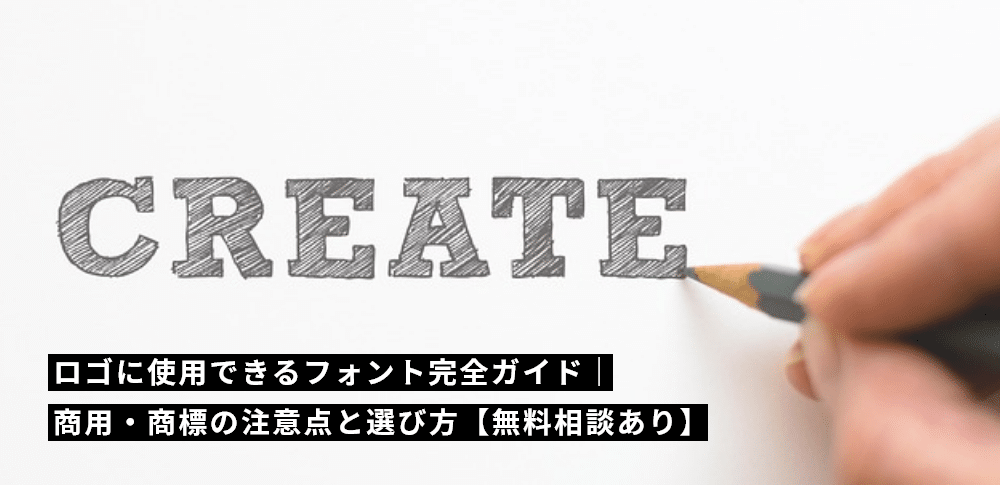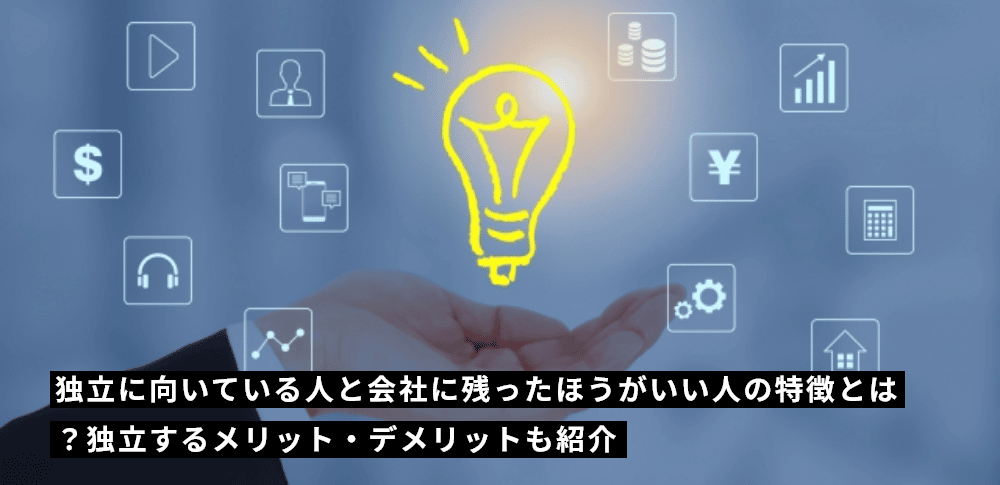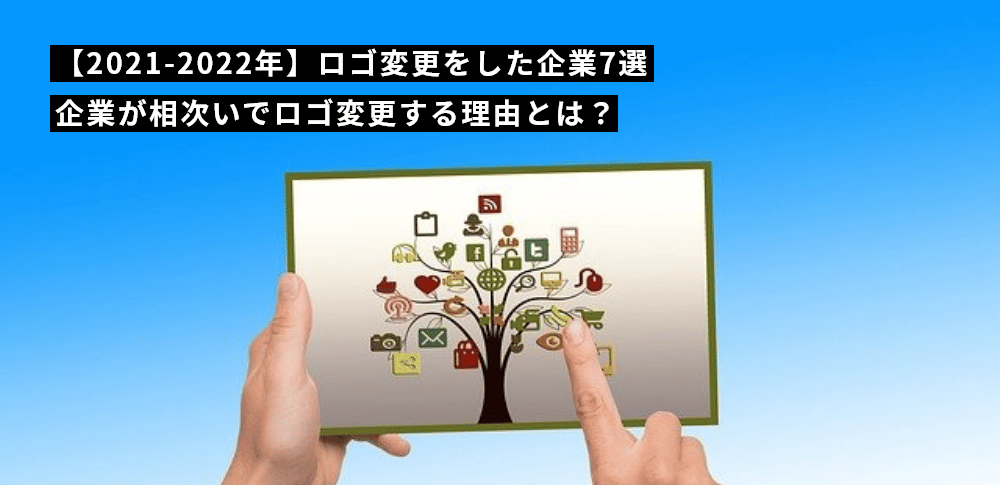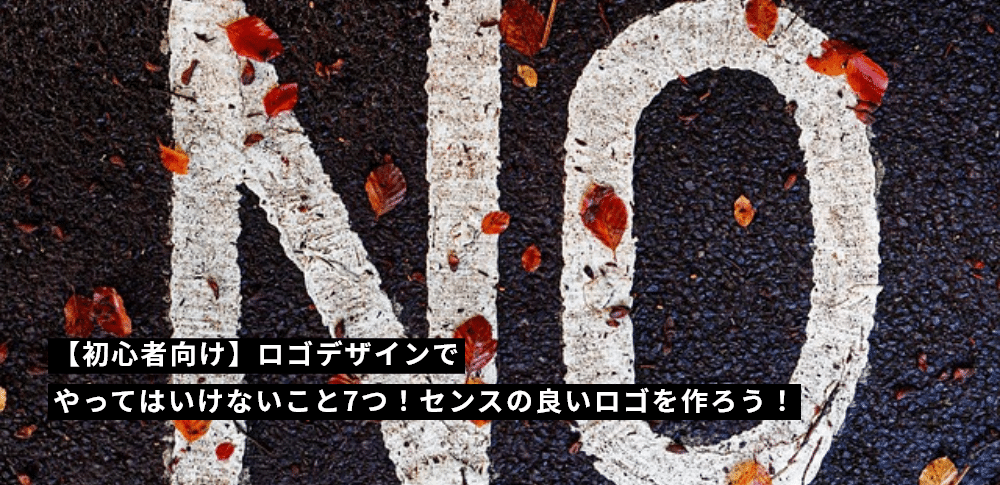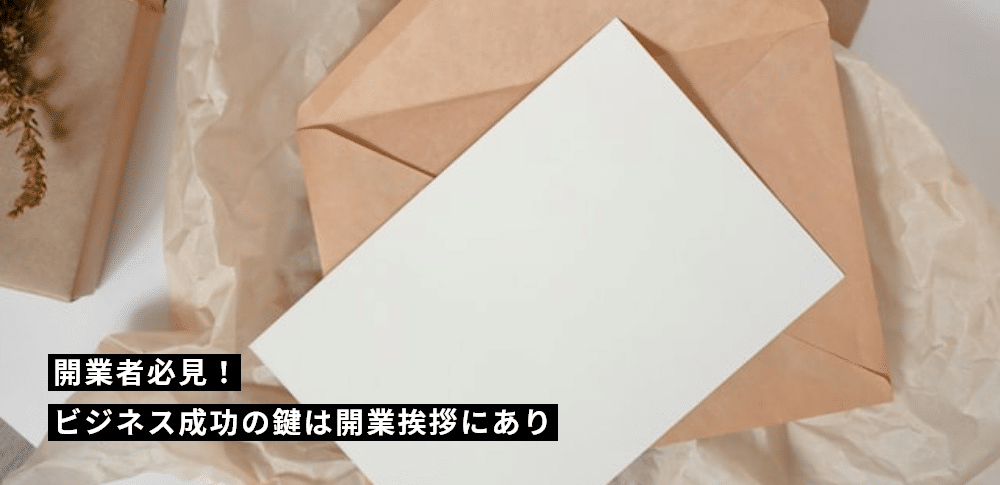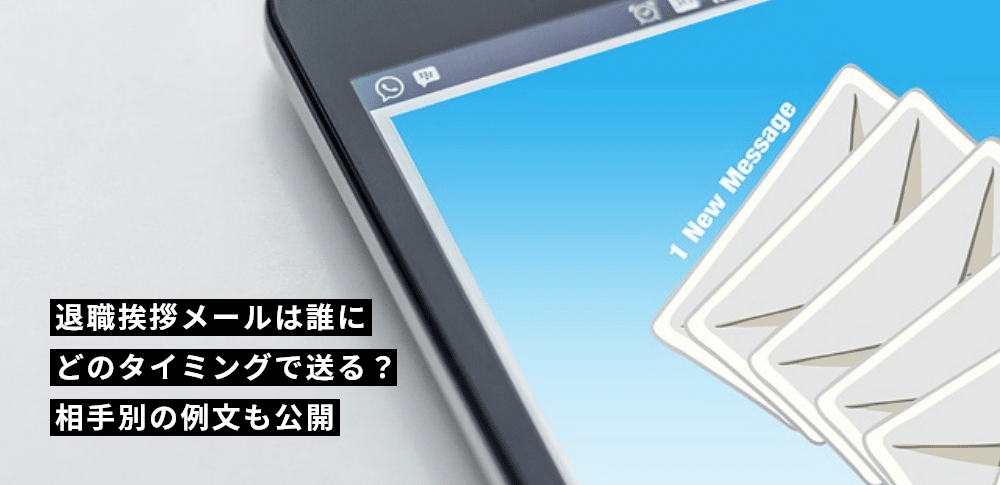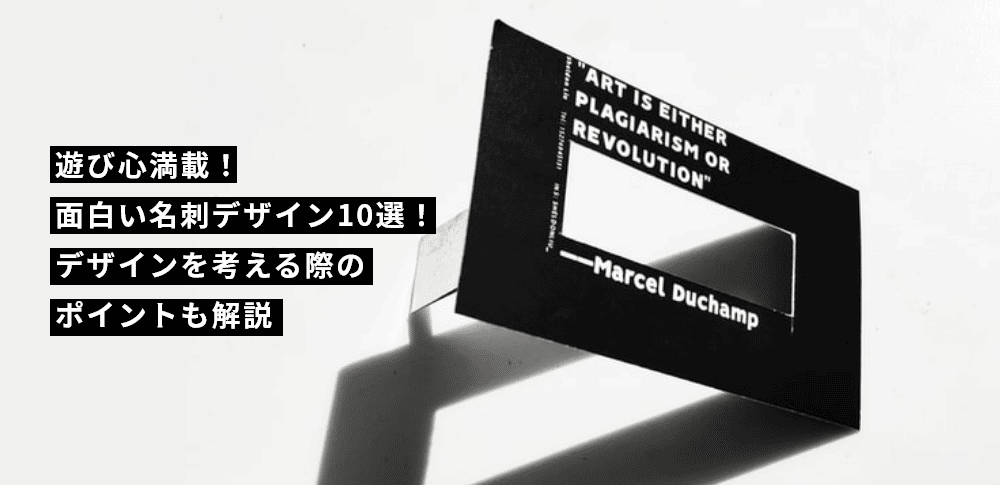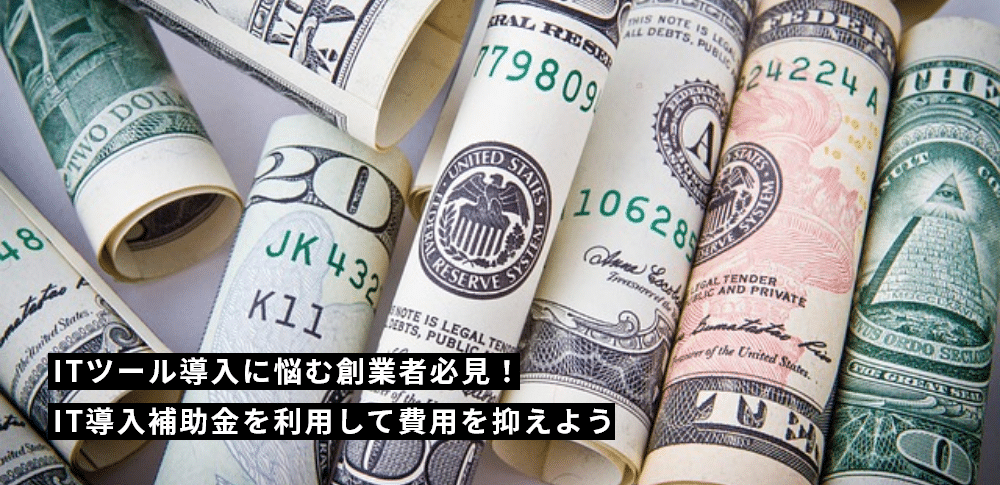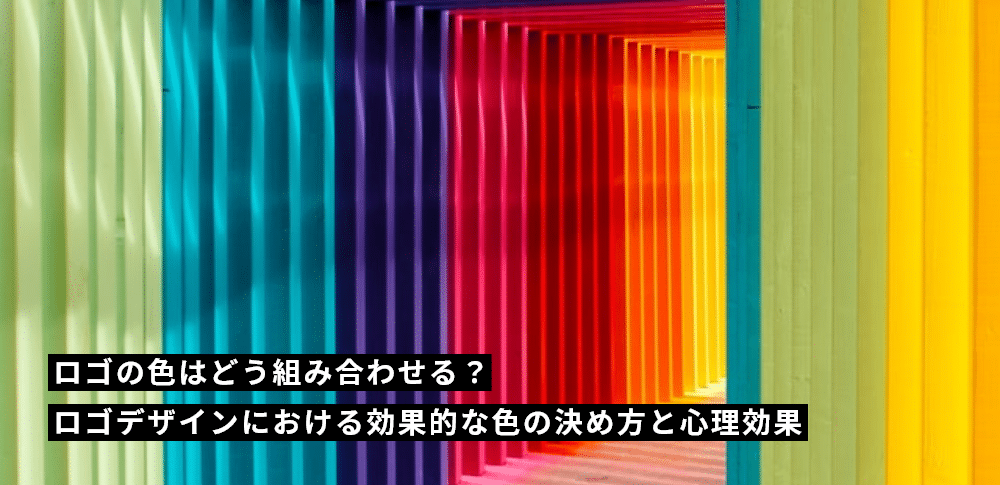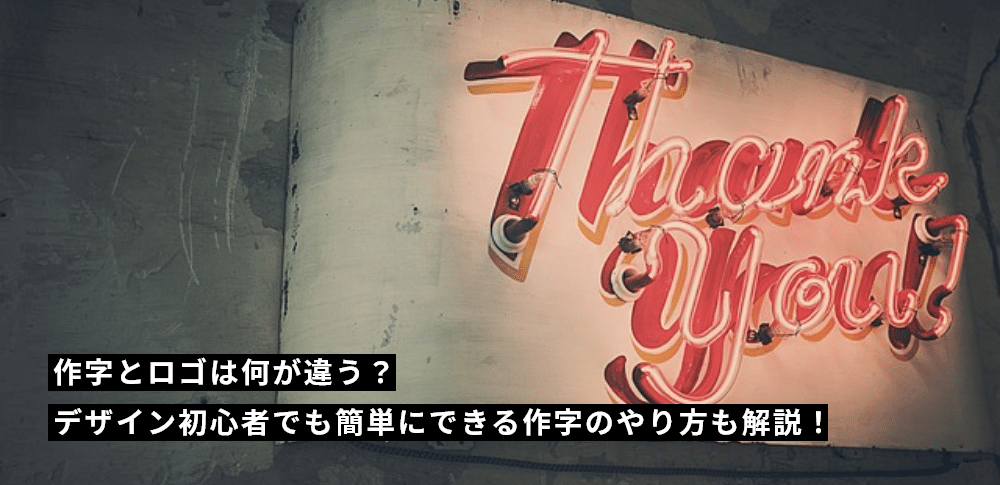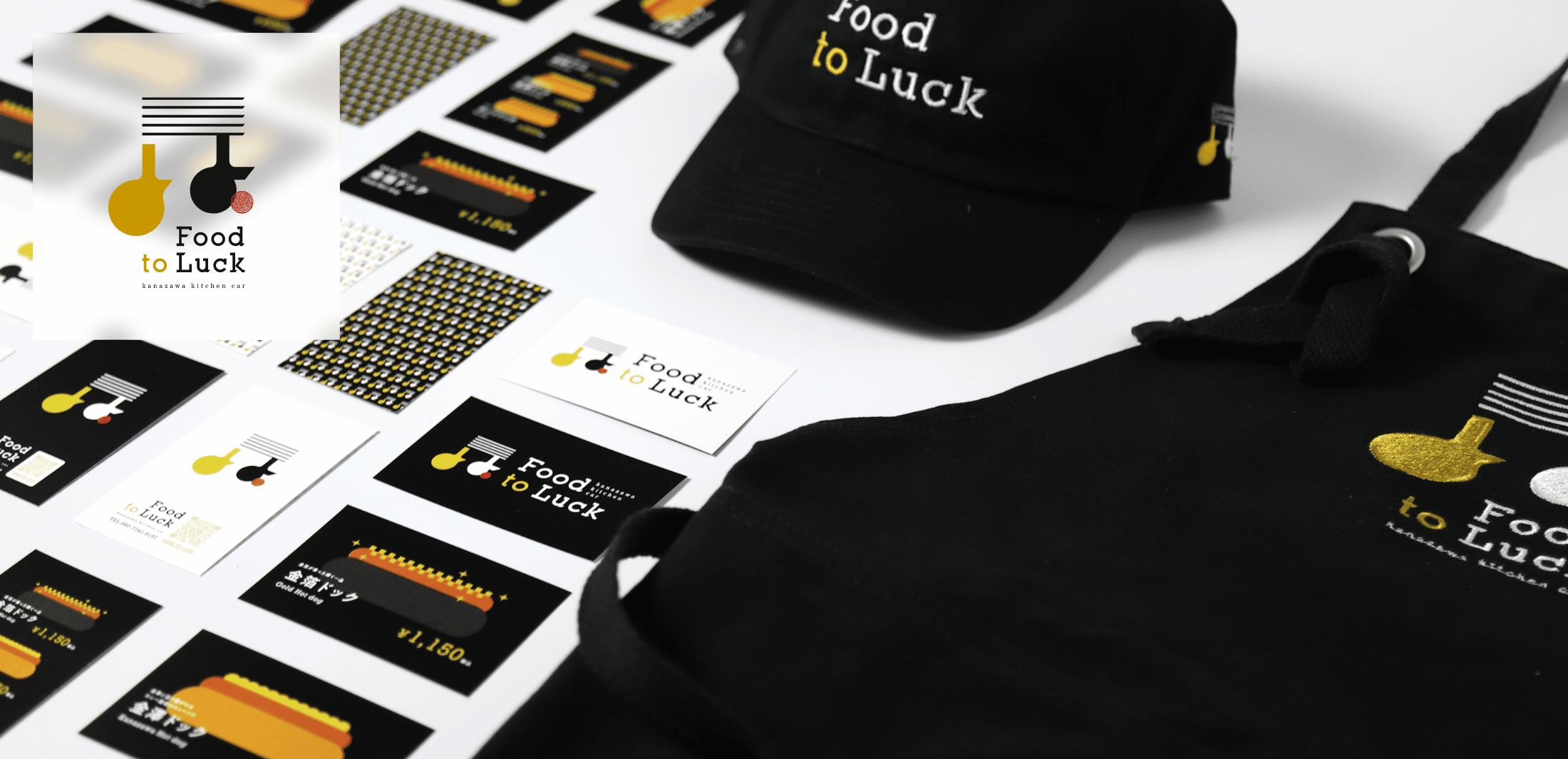RANKING
【社外向け】後任者が挨拶メールを送る際のマナー

人事異動や前任者の急な退職などで担当者が変わった場合、前任者から後任者になったことを連絡する挨拶メールを送ることがマナーになっています。しかし、滅多に担当変更メールを送る機会がないため、どんな内容を書けばいいのか悩まれている方も多いでのはないでしょうか。そこで本記事では、後任者が挨拶メールを送る重要性や、後任の挨拶メールを送るタイミングメールに書く内容について解説します。
目次
後任者が挨拶メールを送る重要性

異動や前任者の退職などのさまざまな理由から担当が変わったことを知らせるために、前任者や後任者がメールを送るのはマナーです。
初めに前任者が丁寧な挨拶とお礼を含む連絡を行い、そのあとに後任者が関係を築くための挨拶メールを送るのが一般的です。
後任の挨拶メールを送るタイミング
取引先のような社外に向けてメールを送る場合、後任の挨拶メールは、前任者から担当変更の連絡を送ったあとにおこないます。
また、連絡は担当変更が決定した時点でできるだけ早く、かつ相手方の事務に支障をきたさないタイミングで連絡することが大切です。
後任の挨拶メールで書く内容
後任の挨拶メールは、引き継ぎの連絡と挨拶の2つの要素を組み込んだ内容にする必要があります。以下では、後任の挨拶メールで書く内容を紹介します。
担当が切り替わるタイミング
担当が切り替わるタイミングで、前任者から担当変更の連絡をおこなっている場合、担当者がいつから変更になるのか連絡する必要があります。
また、前任者と後任者の名前を具体的に挙げて、誰から誰へ担当が変わったのかも伝えてください。
自己紹介
挨拶メールには、引き続き業務や取引をスムーズにおこなう目的があります。
そのため、自己紹介に加えて、一言でも良いので業務に対する意欲を伝えるのがおすすめです。
挨拶へ伺う旨を伝える
相手との関係性によっては、メールだけではなく、直接挨拶へ伺ったほうが良い場合もあります。また、直接挨拶に伺ったほうが顔の見えないメールで済ませるよりも相手からの印象が良くなり、良好な関係性を築きやすくなります。
後任の挨拶メールを送る際のポイント

担当変更メールを送るにあたり、知っておきたいマナーについて紹介します。
後任の挨拶メールを送る際は、以下の3つのポイントに注意しましょう。
件名はわかりやすく
件名を見ただけで、誰からどのような内容のメールが来たかわかるようにする必要があります。件名が分かりにくいと、メールを見てもらえない可能性があります。
そのため、受け取った人が一目でどのような内容かわかるよう、要件と名前を入れて、一目で着任の挨拶だとわかるようにしましょう。
一斉送信は避ける
業務上関わりが深い相手には、「cc」や「bcc」を使って一斉送信するのではなく、「To」を使用して個人宛に送るようにしてください。
「cc」や「bcc」を使用してしまうと、個人情報漏洩にもつながってしまいます。そのため、内容を変える必要はありませんが、宛先だけは個別に設定することをお勧めします。
しかし、時間がなく場合一斉送信せざるを得ない場合は、メール配信システムの活用がおすすめです。
ネガティブな表現は使用しない
担当が変更になっても取引には影響がないことを伝えるために、安心感のある文章を送るよう心がけましょう。
前任者が後任者の紹介をおこなわずに退職してしまった場合や、別件が忙しくなったからなどの理由は社内事情であり、相手方には関係がないことです。
よって、担当変更理由があまり良くなくても、前向きな言葉で表現し、安心して取引を続けられるように配慮することが大切です。
後任の挨拶メールの例文
前任者が事前に連絡していた場合と、していなかった場合の2通りの例文を紹介します。
前任者が事前に連絡していた場合
前任者が事前に連絡できなかった場合
まとめ
担当変更メールは、今後の関係を築くための重要な一通です。担当者変更を知らせるメールは送る内容に配慮が必要ですが、同時に初めてのコミュニケーションの場でもあります。業務的なやり取りだけでなく、自分をアピールして信頼関係を深めることが重要です。
関連記事
-

ITツール導入に悩む創業者必見!IT導入補助金を利用して費用を抑えよう
IT導入補助金を利用すると、ITツールを導入する費用を抑えられます。原則返済が不要という点も大きなメリットです。
-

ロゴの色はどう組み合わせる?ロゴデザインにおける効果的な色の決め方と心理効果
色選びはロゴの第一印象となることに加えて、企業やブランドイメージにも直結する大切なポイントです。ロゴの色の決め方
-

ホテルロゴ一覧&デザイン解説|高級ホテル・ビジネスホテルに学ぶ選ばれるロゴの特徴とは?
有名ホテルロゴの事例やデザインの考え方、外注前の準備ポイントを紹介。高級感と信頼を伝えるロゴを作りたい方は必見で
-

作字とロゴは何が違う?デザイン初心者でも簡単にできる作字のやり方も解説!
似たような意味を持つ、「作字」と「ロゴ」には微妙な違いがあります。作字をやりたいと考えている方の中には、やり方や
-

不動産キャッチコピーガイド|種類・成功の共通点・すぐ使える表現付き!
物件の魅力を伝えるためには、ただ情報を並べるだけでは足りません。 限られたスペースのなかで、興味を
-

東京都で起業する方必見!活用できる創業補助金・助成金を紹介
勤めていた会社を辞めて独立し、東京都で起業を考えている方や学生で起業を考えている方も多いと思います。しかし、起業